美術館・鉄道・お城・お相撲・お友達の話など趣味のブログです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
浮世絵は元々は芸術品でなく庶民が簡単に買える、情報であったり観光絵だったりしました。年末に神社仏閣で戴く初夢用や七福神が書かれたものと同じだったようです。
値段もそば一杯程度だったそうですが、今は北斎冨嶽三十六景46枚一揃えは何十億とか言います。復刻版の浮世絵でも1枚1万5千円以上します。
余り価値が解らなかった時代は輸出の陶磁器のクッションに使われたりして丸められていたそうです。それがパリの万博でこの浮世絵などが陶磁器と共に印象派の画家達に価値が見出され彼らがその構図などを見習ったりして模倣をして作画をしている事は有名です。
今はゴッホの絵は凄い評価をされていますが生存中は売れず弟が一生懸命援助しています。そして亡くなってから評価されています。何も解らない私はひまわりをありがたく見させていただいたりしますが誰かが評価して認められるとなぜかありがたく感じます。(権威に負けているのか自分が解らないのですがピカソやジャクソンポロックなど今だに解りません。)
印象派も当時のフランスでは評価されずアメリカ人によって評価されてから再評価されています。明治の富国強兵、文明開化と言う御旗で日本文化品の多くが海外に渡っています。
そのため多くの浮世絵も日本より海外に収集されています。岡倉天心などによるボストン美術館、大英博物館、現在京都文化博物館で行われているホノルル美術館の北斎展と今更言ってもしょうがないですがちょっと残念です。結局数少ないコレクターが収集した浮世絵だけが国内に残って小さな専門美術館として開館している状況です。
国内にもバラバラに所蔵しています。東京国立博物館、東京大学、慶応大学など沢山あるようです。これを一つにして保存維持復元していけば将来の財産になると思うのですがこれも中々難しいようです。パリのルーブルは古い所蔵、オルセーは印象派以降から、ポンピドゥは近代芸術と区分けされて収集するのは解りやすい。
今は都内で少額で見せて戴いています。何10億と云う価値を千円からワンコインだったり凄いのは無料だったりこれでは維持も中々難しいようです。
当然海外から借りてくれば経費もかかり高い入場料になります。大きい美術館は宣伝費を掛け多くの集客をしています。同じ冨嶽三十六景46枚ニューオータニでは800円、平木浮世絵美術館では東海道53次500円、サントリー美術館では借りものですから1300円、森アーツセンターでは国芳展1500円、同じ国芳展太田記念美術館では1000円です。それでも知らないのか宣伝が旨いのか圧倒的に集客をしているようです。
そんな中、普段行く小さな美術館で感謝しながらゆっくり見させていただこうと思っています。
値段もそば一杯程度だったそうですが、今は北斎冨嶽三十六景46枚一揃えは何十億とか言います。復刻版の浮世絵でも1枚1万5千円以上します。
余り価値が解らなかった時代は輸出の陶磁器のクッションに使われたりして丸められていたそうです。それがパリの万博でこの浮世絵などが陶磁器と共に印象派の画家達に価値が見出され彼らがその構図などを見習ったりして模倣をして作画をしている事は有名です。
今はゴッホの絵は凄い評価をされていますが生存中は売れず弟が一生懸命援助しています。そして亡くなってから評価されています。何も解らない私はひまわりをありがたく見させていただいたりしますが誰かが評価して認められるとなぜかありがたく感じます。(権威に負けているのか自分が解らないのですがピカソやジャクソンポロックなど今だに解りません。)
印象派も当時のフランスでは評価されずアメリカ人によって評価されてから再評価されています。明治の富国強兵、文明開化と言う御旗で日本文化品の多くが海外に渡っています。
そのため多くの浮世絵も日本より海外に収集されています。岡倉天心などによるボストン美術館、大英博物館、現在京都文化博物館で行われているホノルル美術館の北斎展と今更言ってもしょうがないですがちょっと残念です。結局数少ないコレクターが収集した浮世絵だけが国内に残って小さな専門美術館として開館している状況です。
国内にもバラバラに所蔵しています。東京国立博物館、東京大学、慶応大学など沢山あるようです。これを一つにして保存維持復元していけば将来の財産になると思うのですがこれも中々難しいようです。パリのルーブルは古い所蔵、オルセーは印象派以降から、ポンピドゥは近代芸術と区分けされて収集するのは解りやすい。
今は都内で少額で見せて戴いています。何10億と云う価値を千円からワンコインだったり凄いのは無料だったりこれでは維持も中々難しいようです。
当然海外から借りてくれば経費もかかり高い入場料になります。大きい美術館は宣伝費を掛け多くの集客をしています。同じ冨嶽三十六景46枚ニューオータニでは800円、平木浮世絵美術館では東海道53次500円、サントリー美術館では借りものですから1300円、森アーツセンターでは国芳展1500円、同じ国芳展太田記念美術館では1000円です。それでも知らないのか宣伝が旨いのか圧倒的に集客をしているようです。
そんな中、普段行く小さな美術館で感謝しながらゆっくり見させていただこうと思っています。
PR
江戸時代は多色摺の浮世絵の錦絵には多くのお相撲さんが描かれています。明治になると印刷技術の発展で浮世絵も姿を消していきます。
その後京都版画院の尽力で相撲錦絵が復活、その版画を中心に相撲博物館が所蔵する大正から現代までの相撲版画を展示しています。今回はその他に版木、彫刻刀、摺道具や版画が出来る過程を版木を並べながら解りやすく展示しています。
次は三段構えで吉田司家の考案?、上段、中段、下段の各構えで特別な日に横綱や大関が行うようで、写真は男女ノ川、双葉山、部屋開きや奉納相撲などで行うようです。天皇陛下が早く回復され天覧相撲にお越しになれれば見られるかもしれません。
版画は雪の蔵前国技館や北の湖、千代の富士など現代のお相撲さん、昔の若乃花、栃錦、柏戸などポスター表紙は白鵬などが描かれています。現高砂親方の大関朝潮なども浮世絵のお相撲さんらしく描かれています。
大相撲の非開催時の平日と言う期間が開館ですので無料ですがあまり知られていない事もあり何時行ってもゆっくり見られます。今日は外人さんのツアーだったようで普段よりは多くの人がいました。
また相撲土産もお店があけています。東京へお越しの際の一つの観光コースにも最適だと思うのですが。
この駅のホームは4両編成対応のホームで現在京急は6両編成ですから川崎方面からこの駅で下車する時は前の4両までに乗っていないとドアが開かず次の駅まで連れて行かれてしまいます。そんな事も平成25年までです。
狭い会場ですが無料で拝見できる家族的な場所です。今回は北斎の冨嶽36景の江戸、神奈川を中心として展示されています。勿論有名な凱風快晴、山川白雨もあります。また北斎生涯唯一の双六絵「鎌倉・江の嶋・大山 新板往来双六」(初摺)も展示されています。
その他に諸国滝廻り3点など北斎らしい構図の浮世絵です。また後年は肉質画が多くなりその中で数点展示されています。また初めての絵としては初期のまだ人気もなく勝春朗時代の両国橋夕涼花火見物の絵も展示されています。
次回は3月5日から24日まで大蘇芳年の月百姿展(前期)です。
龍子は戦争で子供を亡くし相次いで妻も他界しその7回忌になるんでしょうか昭和25年65歳の時に三女と句の冬扇を主催している深川正一郎の三人で6年かけて廻っています。
龍子は建築が趣味で記念館もアトリエも自身の設計ですが今回は「草描」と称して札所の建築を中心に今まで手がけていなかった風景画を題材に描くこと、88ヶ所と言う順番に巡ると言うことにも興味を持っていたようです。
展示は墨絵を中心とした色紙絵と下に紀行直筆原稿、いくつかはスケッチが展示されています。見ごたえは充分、時間も掛かります。途中から腰が痛くなり原稿を読め無くなりましたので図録を購入しました。
龍子は当時大変多忙だったようです。春秋の自身の青龍会の展示作品、年数回の個展、依頼による製作があり毎年1週間位の遍路を取るには当時ですから夜行列車で行き関西の展示会の作品並べをして主催者、顧客に挨拶をしてから四国へ船で渡ったようです。
帰ったら空いた時間に色紙絵を描き、青龍会用にも色紙の5,6倍の大きさの絵も描いています。ですから関西のデパートでの展示会の仕事をして深川氏の雑誌の裏表紙絵、自身の展覧会用の絵、俳句と一つの旅で幾つもの目的を持って作業をしていたようです。勿論、妻子の供養もあります。凄いのは合間を縫って渦潮見学、金毘羅宮で伊東若冲、円山応挙の絵なども見て、毎夜句会のも出席しています。
スケッチと同じような絵だったりスケッチは詳細に描かれているが色紙絵はかなり俯瞰して描かれたり、お遍路さんが入ったりとやはり広重の浮世絵と同じように台風で倒れた木だけだったり、お寺の本堂だけだと88ヶ所もあるので色々な角度から書かれています。大きい自身の展示会用の絵も色紙と同じ構図だったりアップした作品になったり全く違う角度からの絵だったりしています。青龍会での絵は全部売れてしまい今は手元にはなく、色紙、原稿も深川氏の手元へ行っています。今回の展示はそんな龍子の里帰り展示です。
時間的な問題もあり毎年春秋と言う事もあり順番には廻っていないようです。しかし昔の人で楽して難所を越えることには反対して、そんな廻り方は後で悔やむと7時間掛けて歩いたりしています。
現在もお遍路は静かなブームだそうで50歳から70歳位の人が多く、女性が6割近いそうです。今では自家用車で8,9日、団体バスで12,3日、全部徒歩で4,50日掛かるそうです。
今回のような展示は初めて見ました。私もただ散策だけでなく絵は描けないから俳句でもまた始めようか、今は途中郵便局スタンプ、和菓子屋さん、美術館、寺社と廻っていますから此れに俳句?川柳でも良いから始めてみようと思いました。多忙の人ほど時間の使い方が上手のようです。一流芸能人が絵画展に出品したり何処にそんな時間があるんだと思ってしまいます。私は時間が一杯あるから無駄に過ごしているんでしょうか。
龍子記念館HP
棟方志功といえば版画、ベニスのピエンナーレでの版画大賞「二菩薩釈迦十大弟子図屏風」とピンク色の天女図が思い出されます。目が悪く硬い板に大きな彫刻刀で勢いよくカットしていく画面など。
今回はこの他に棟方志功の長年交流のあった京都の山口邸でありとあらゆる屏風、ふすま、板戸などに水墨画や色絵画などで病の亭主を慰めるため書いた東京
浮世絵から版画作品を少しは見ていますがこの人の版画は世界的に評価をされていますが私にはまだ芸術が良く解っていなく、なんで是がと思うものが多くあります。
襖の漢字はそうでもないですが板戸などにひらがなや漢字で万葉集などが書かれています
前回は棟方志功が先生と呼んだ平塚運一の版画展を見ましたが同じ海外で評価された版画のタイプが全く違います。まぁ平塚運一は評価されたのはヌードですが、天女や二菩薩釈迦十大弟子図屏風などが無かったらこの展覧会は何だと思ってしまいます。
今、国立近代美術館で開催されているピカソを超えたと言われるジャクソンポロックのあの絵の具を垂らした絵が何で2億円もするんだと思う私ですからどうも芸術は解らない。かと言って写実絵全部が素晴らしいとは思わないのですが。難しい。
文句ついでに百貨店の展覧会はどうして出展リストを作らないんだろうか、有りますかと聞けば図録はありますと言われてしまいます。図録を作る時間があるんならたった1枚の出典リストくらいすぐできると思うのに。
深川資料館では企画展として「広重の旅と名所絵」を今年10月まで広重の作画姿勢などを検証しながらの展示会を長期開催しています。(浮世絵は少なくコピーです。)しっかり研究された展示ですので此処で浮世絵を見てきた纏めとして広重を考えました。
まず、歌川広重は寛政9年定火消同心の子として、親は若くして亡くなり家業を継ぎます。その傍ら歌川豊広に入門して師の「広」と自分の名前重右衛門の「重」をとって広重と言う画号になります。
27歳で専業の画工になり文政13年斉号を一幽斉と改め「東都名所」を大判横絵十枚揃えで舶来の化学染料のベロ藍を使い遠近感を持たせた手法で新しい浮世絵として世に出していきます。(私の今月の絵で)
当時の浮世絵は役者絵、芸者などの美人画などが主流でした。東都名所から出世作になる「東海道五十三次」の当時としては55枚の揃い物が大あたりをします。
その風景画ですが実景実写でなく意図的に様々な改変が加えられています。同じように北斎もそうですが実際に歩いて居なく「江戸名所図会」などの色々な出版されている「名所図会」を写しているのではという疑惑があります。
広重の作画姿勢になりますがまず①自分が書きたくて書いたものである。版元と言われる出版に対してお金を出している人の意向。②旅に憧れる人々の抱く土地のイメージ、風土気候、食べ物、名所旧跡など購買者の意向に沿うように興味が湧くような形に描いています。
広重の現在解っている旅日記は①甲州行日記②甲州日記写生帳③狩野山行日記④房総行日記です。またスケッチ帳もあります。江戸名所写生帖、大英博物館に所蔵されている中山道のスケッチ帖などが解っているものだそうです。
広重はそのスケッチを何度も利用したり、全く違う構図にしたもの、名所図会などを種本にしただろうと思われる構図など色々あります。広重が東海道を実際に歩いたかは不明ですが大英博物館のスケッチ帖から推定すると往路の中山道との合流地点の草津から京都まで、帰路の名古屋から江戸までは解っています。
広重は江戸名所関係だけで1000枚以上書いています。また東海道を主題にした東海道物も20種類以上制作しています。ですから同じ構図だけでなく東海道名所図会や人気の東海道中膝栗毛などの構図やモチーフを参照している。四条派や中国絵画の影響、作品の季節・時間・天候などの演出を組み込むなどをしています。
また街道物が受けた背景としては東海道が整備され庶民も近隣の大山、江ノ島、鎌倉などの旅、富士山、伊勢参りなど講による代表者の旅が盛んに行われて庶民が旅に憧れていた。
十返舎一九の東海道中膝栗毛の大ヒットなどが背景にあり東海道中膝栗毛の出版から30年位経ってから広重の東海道五十三次が出版し版木が壊れる位の大ヒットになります。
重なりますが版元の意向、購買者の期待に沿うため手前を大きく過大に描き遠近法を用いたり実際とは違う俯瞰的に描いたり広重の絵画姿勢も他の作者との差別的描いていたのかもしれません。
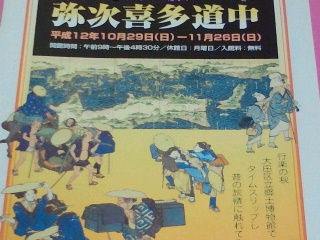 東海道中膝栗毛
東海道中膝栗毛
十返舎一九の江戸時代後期を代表する滑稽本、1802年に初編刊行されました。膝栗毛は膝を栗毛の馬になぞらえた言葉で徒歩旅行をさします。
旅人は弥次喜多と言われる栃面屋弥次郎兵衛と喜多八で伊勢参宮と京都、大阪見物に旅に出ます。日本橋から旅立ち道中面白おかしく兄弟になったり手代になったり宿場宿場で面白おかしく珍道中を繰り広げます。
江戸時代最大の大ヒット作となり明治時代まで増刷を繰り返します。また好評の為中国、四国、中山道などを旅する続編も刊行されています。今で言えばテレビドラマ水戸黄門のようです。
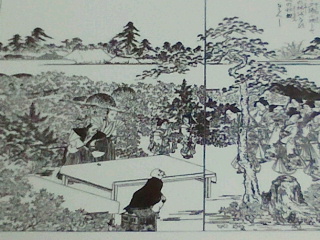 東海道名所図会
東海道名所図会
江戸時代になると東海道も整備され人々の移動が容易になり庶民も様々な旅に出たりその土地土地に関心が集まります。そこで具体的な詳細な挿絵が挿入された名所図会が発行されます。寛政9年現地取材をしたこの本が出版されます。斎藤月岑親子三代で7巻20冊で鳥瞰図を用いた地誌紀行本で長谷川雪旦の挿絵が有名です。また多くの名所図会が刊行されています。
深川江戸資料館HP http://www.kcf.or.jp/fukagawa/event_detail_030100600101.html
まず、歌川広重は寛政9年定火消同心の子として、親は若くして亡くなり家業を継ぎます。その傍ら歌川豊広に入門して師の「広」と自分の名前重右衛門の「重」をとって広重と言う画号になります。
27歳で専業の画工になり文政13年斉号を一幽斉と改め「東都名所」を大判横絵十枚揃えで舶来の化学染料のベロ藍を使い遠近感を持たせた手法で新しい浮世絵として世に出していきます。(私の今月の絵で)
当時の浮世絵は役者絵、芸者などの美人画などが主流でした。東都名所から出世作になる「東海道五十三次」の当時としては55枚の揃い物が大あたりをします。
その風景画ですが実景実写でなく意図的に様々な改変が加えられています。同じように北斎もそうですが実際に歩いて居なく「江戸名所図会」などの色々な出版されている「名所図会」を写しているのではという疑惑があります。
広重の作画姿勢になりますがまず①自分が書きたくて書いたものである。版元と言われる出版に対してお金を出している人の意向。②旅に憧れる人々の抱く土地のイメージ、風土気候、食べ物、名所旧跡など購買者の意向に沿うように興味が湧くような形に描いています。
広重の現在解っている旅日記は①甲州行日記②甲州日記写生帳③狩野山行日記④房総行日記です。またスケッチ帳もあります。江戸名所写生帖、大英博物館に所蔵されている中山道のスケッチ帖などが解っているものだそうです。
広重はそのスケッチを何度も利用したり、全く違う構図にしたもの、名所図会などを種本にしただろうと思われる構図など色々あります。広重が東海道を実際に歩いたかは不明ですが大英博物館のスケッチ帖から推定すると往路の中山道との合流地点の草津から京都まで、帰路の名古屋から江戸までは解っています。
広重は江戸名所関係だけで1000枚以上書いています。また東海道を主題にした東海道物も20種類以上制作しています。ですから同じ構図だけでなく東海道名所図会や人気の東海道中膝栗毛などの構図やモチーフを参照している。四条派や中国絵画の影響、作品の季節・時間・天候などの演出を組み込むなどをしています。
また街道物が受けた背景としては東海道が整備され庶民も近隣の大山、江ノ島、鎌倉などの旅、富士山、伊勢参りなど講による代表者の旅が盛んに行われて庶民が旅に憧れていた。
十返舎一九の東海道中膝栗毛の大ヒットなどが背景にあり東海道中膝栗毛の出版から30年位経ってから広重の東海道五十三次が出版し版木が壊れる位の大ヒットになります。
重なりますが版元の意向、購買者の期待に沿うため手前を大きく過大に描き遠近法を用いたり実際とは違う俯瞰的に描いたり広重の絵画姿勢も他の作者との差別的描いていたのかもしれません。
十返舎一九の江戸時代後期を代表する滑稽本、1802年に初編刊行されました。膝栗毛は膝を栗毛の馬になぞらえた言葉で徒歩旅行をさします。
旅人は弥次喜多と言われる栃面屋弥次郎兵衛と喜多八で伊勢参宮と京都、大阪見物に旅に出ます。日本橋から旅立ち道中面白おかしく兄弟になったり手代になったり宿場宿場で面白おかしく珍道中を繰り広げます。
江戸時代最大の大ヒット作となり明治時代まで増刷を繰り返します。また好評の為中国、四国、中山道などを旅する続編も刊行されています。今で言えばテレビドラマ水戸黄門のようです。
江戸時代になると東海道も整備され人々の移動が容易になり庶民も様々な旅に出たりその土地土地に関心が集まります。そこで具体的な詳細な挿絵が挿入された名所図会が発行されます。寛政9年現地取材をしたこの本が出版されます。斎藤月岑親子三代で7巻20冊で鳥瞰図を用いた地誌紀行本で長谷川雪旦の挿絵が有名です。また多くの名所図会が刊行されています。
深川江戸資料館HP http://www.kcf.or.jp/fukagawa/event_detail_030100600101.html
 にゃんとも猫だらけ第二部化け猫騒動を今月26日まで豊洲の平木浮世絵美術館で開催中です。約40点歌舞伎などで上演した岡崎八つ橋村の化け猫騒動を中心に展示されています。
にゃんとも猫だらけ第二部化け猫騒動を今月26日まで豊洲の平木浮世絵美術館で開催中です。約40点歌舞伎などで上演した岡崎八つ橋村の化け猫騒動を中心に展示されています。説明によると文政10年「独道中五十三駅」で三代目尾上菊五郎の演じた岡崎の化け猫は人気演目になり沢山の脚色により演じられたそうです。
話は旅の娘が一夜の宿を借りた古寺で深夜、十二単を着た老婆が現れ、様々な怪異を見せるが武者に猫の精の本性を見顕されて虚空に飛び去るというあらすじだそうです。
国芳、国貞、芳幾、芳年など多くの作家が書いているようです。今回は化け猫の話でこの寒空にと思いながらお邪魔しました。思ったより迫力がある怖さの絵はなかったのでちょっとホッとしました。
次回3月3日からは第三部猫と遊ぶになります。浮世絵にちょこっと猫が多くさりげなく描かれていますがさてどんな美人画の中に猫が出てくんでしょうか。
平木浮世絵美術館HP
http://www.ukiyoe-tokyo.or.jp/index.html
館内には品川から弥次さん喜多さんの旅が始まります。目的はお伊勢さん参拝ですが伊勢から奈良、京都、大阪天王寺までの画になっています。
60枚見ながら下のキャプションを読んでいくと結構な時間がかかり、腰が痛くなります。とてもきれいな絵で木版画ですが広重などの浮世絵のきつい色でなくパステル、水彩画的な色調です。
前回此処を訪れたのはこの木版画を見る為だったのですが次の日からで駄目でその後会期は2週間でしたが風邪をひいたりして終わり間際になってしまいました。もう一度みたいものもありましたが残念。
時間がある時、寒い日、雨の日などは部屋できっぷを整理しています。色々な形状のきっぷですからストックする特殊ファイルをまず「目白の切手博物館」、駅前の「エスケースタンプ」で購入。このファイルが結構高く、重いので数冊づつ買っていました。想像しているよりすぐなくなってしまいます。
ニューオータニ美術館の新春展は29日まで。1度見ていますから今回は見たいと思っている日本画、浮世絵肉質画のコーナーへ、横山大観、下山観山、菱田春草、歌川豊春、北尾政演、北尾政美など。軽く食事をして地下鉄で渋谷へ。
目黒から大森駅東口駅前のダイニングバー「國」で一杯、時間調整して近くのいわし料理「西鶴」でまた一杯。ごきげんで帰宅。
左の写真は大正時代の四谷見附橋の欄干、隣が現在の欄干デザインは同じようです。右は昔の外堀、今は空掘りで上智大学のグランド。
その他にビデオで江戸切子などの制作などを放映したり300人位収容の小ホールなどがあります。
広重の旅と名所絵は、広重の制作姿勢として実際に旅したもの、名所案内記などを材料にして独自の構図法やオリジナリティで描いた独創性を幾つかの旅の中、そこで書いた旅日記、絵日記などから読み解くと言うテーマです。
箱根までの旅、これは金沢八景、鎌倉、江ノ島、大山、箱根など当時から庶民に人気な行楽地を4人で巡っています。此処では本物の浮世絵は1枚もなく全てコピーの図で紹介されています。
面白いのは金沢八景から鎌倉を目指すのは朝比奈峠を越えて鎌倉へ抜けるのをわざわざ浦賀へ行っています。なぜだったのか、ペリーはまだ来てはいませんが外国船は往来していますが絵には外国船は描かれていません。同行の井上文夫の手鑑には目的が物見遊山だけではなかったとも書かれているそうです。
数少ない旅日記には途中の景色だけでなく食べ物、出会った人などがスケッチされたりしています。大森の磐井神社のすず石などもスケッチしています。箱根では宿の宣伝ポスター?なども依頼されて描いているようです。
今回展示ではこの他に甲府、房総などの旅を自身の日記などと比較して検討されています。ただ浮世絵を見るだけでなく広重の制作姿勢や依頼された作画、参考にした名所図などと見比べる楽しい機会でした。
次回の企画展の東海道名所膝栗毛画貼も楽しみにしています。
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
カウンター
カテゴリー
最新コメント
最新記事
(04/17)
(04/17)
(04/16)
(04/15)
(04/14)
(04/13)
(04/12)
(04/11)
(04/10)
(04/09)
(04/09)
(04/08)
(04/07)
(04/06)
(04/05)
(04/05)
(04/04)
(04/04)
(04/03)
(04/03)
(04/02)
(04/01)
(03/31)
(03/30)
(03/30)
プロフィール
HN:
パパリン
性別:
男性
趣味:
なんでも収集
ブログ内検索
アーカイブ
アクセス解析

