[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
先月還暦を迎えた後輩君から私のやっているトレーニングをやりたいという事でまず準備としてウエアー、シューズなどを一緒に買いに行きました。
時間が十分あるので多摩川の土手をツーリング?しようという事になりそれなら旧川崎宿に浮世絵が展示しているからと誘った。広重の保永堂版東海道五十三次全55枚が見られるのは今年最後でしょうからもう一度見ておきたかった。
新しくできた東海道かわさき宿交流館、今回のオープニング企画の目玉が川崎砂子の里資料館提供の保永堂版「東海道五十三次」55枚ですが、ここでは表紙、変わり絵、後摺りなども何枚かあります。
新しい施設ですのでかなり多くの人が来館しています。1階はビデオで川崎宿をおさらいができます。そして六郷の渡しを渡ったところにあった万年屋をお休みどころにした模型、売店。
2階が映像や模型で川崎宿を勉強できるようなスペース。
3階が今回は東海道五十三次の展示しているイベントスペースと川崎を昔から現代までを比較できる常設展示スペース。
4階が会議室や多目的スペースになっています。
子供から大人までが川崎の学習ができるようになっています。裏には有料ですが駐輪スペースがあります。入場無料、月曜休館。(写真はお土産で買った復刻版万年屋奈良茶飯)
斜め前がよく行く川崎砂子の里資料館で今月は先月からの続きで富士山の浮世絵75枚展示。前回書きましたので展示内容は省略。来月も富士山の浮世絵第三部となっているようです。此方も入場無料、日祭日休館。
今でも富士山は人気ですが、昔も富士山は人気で多くの絵師が描いていますから沢山の浮世絵があります。何度見ても素晴らしい。後輩君はいきなり初めての浮世絵鑑賞で140枚近くを見たので疲れてしまったようです。
 東急線各駅停車の旅で現在東急東横線を歩いています。今日は中目黒を歩いていました。中目黒といっても目黒川の桜並木は有名ですが、秋のこの時期、中目黒には何があるんだろうと、川以外をと歩いていましたら「郷さくら美術館」という電信柱に矢印の看板が。
東急線各駅停車の旅で現在東急東横線を歩いています。今日は中目黒を歩いていました。中目黒といっても目黒川の桜並木は有名ですが、秋のこの時期、中目黒には何があるんだろうと、川以外をと歩いていましたら「郷さくら美術館」という電信柱に矢印の看板が。
初めて聞く美術館名で何の美術館か?結局は目黒川を越えたすぐに黒い建物が右側にありました。
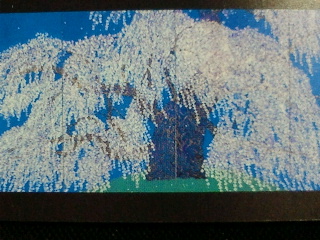
 昭和の日本画の作家を収集した美術館で「花木画」「風景画」「人物画」「動物画」などその時のテーマにより展示しているようです。東京館の他に福島の郡山にも本館があるようです。
昭和の日本画の作家を収集した美術館で「花木画」「風景画」「人物画」「動物画」などその時のテーマにより展示しているようです。東京館の他に福島の郡山にも本館があるようです。
 今回は時期的に菊の絵が多く展示されています。日本画はあまり作家は知りませんが川端龍子の弟子の牧進、中島千波程度しか知りませんが、河股幸和、本多功身、平松礼二、岡信孝などの作品は好きな絵でした。
今回は時期的に菊の絵が多く展示されています。日本画はあまり作家は知りませんが川端龍子の弟子の牧進、中島千波程度しか知りませんが、河股幸和、本多功身、平松礼二、岡信孝などの作品は好きな絵でした。
とても見やすい美術館で今回はざっと見ましたが時間が許せばゆっくりみたい美術館です。東急中目黒駅から近く、落ち着いた美術館です。
先月に続いて富士山世界文化遺産登録記念の「富士山」の浮世絵75点をあまり広くない会場にびっしりと展示しています。
今回も広重の絵を中心に展示しています。一般的な東海道五十三次は、新設された「東海道かわさき宿交流館」に開館記念の目玉イヴェントとして展示していますので,此方では、狂歌入り、行書の東海道五十三次の富士山の描かれた浮世絵を展示。
富士山は昔から日本人の憧れの山ですから多くの絵師が描いています。絵師名だけでも、喜多川歌麿、二代歌麿、北尾政美、葛飾北斎、歌川国貞、国芳など。
今回初めて見た絵師作品、菊川英山、柳々居辰斎、二代目鳥居清倍など。まだまだ知らない作家が多い。
東海道かわさき宿交流館オープン
10月1日に旧東海道川崎宿、川崎砂子の里資料館の斜め前に立派な交流館がオープンしています。
常設展示、企画展示、今回は歌川広重の東海道五十三次を全部展示中。(砂子の里資料館提供)、これからは浮世絵展示、現代美術展などを予定。またご隠居寄席なども。
これから観光以外に地域活動、地域交流の場としての施設を目指していくようです。なかなか立派な施設で、浮世絵、落語といったものからボタンで川崎宿、現代の川崎などが映し出される近代設備も用意されています。
一階では川崎の久寿餅など名物や絵葉書などを販売、川崎宿と言えば万年屋の奈良茶飯ですがなんと売っていました。釜飯スタイルで初めて戴きましたが、製造は何ととなりの大田区千鳥、まぁ近いんだからいいか。http://kawasakishuku.jp/
月曜休館、入場無料、川崎区本町1-8- 044―280―7321
東京国立近代美術館の常設展、企画展の竹内栖鳳展で時間もあり常設展も見られますので久しぶりにお邪魔。東京国立近代美術館は昭和27年京橋にオープンしましたが、所蔵作品が多くなり現在地の竹橋近くに昭和44年新館がオープン。この建物はブリヂストンの創業者石橋正二郎氏の個人的な寄付による寄贈建物だそうです。
所蔵は明治後半から現代美術品の収蔵約12000点(絵画、彫刻、水彩画、素描、版画、写真など)収蔵したした作品の常設展示をしています。(年数回入れ替え)感じとしてはパリのオルセー美術館的なものでしょうか。東京国立博物館がルーブルに当たるのでしょうか。
その展示作品は年に数回入れ替えますが展示数は200点近くだそうです。勿論そんな多くの作品は見られませんから此処では日本画、洋画だけにしてもかなり時間がかかりますが展示作品は其処らへんの企画展ではかなわないでしょう。
ランダムに名前を書いても凄い。加山又造、梅原龍三郎、横山大観、藤島武二、金山平三、岸田劉生、萬鉄五郎、安井曾太郎、岡本太郎、藤田嗣治、奥村土牛、速水御舟、竹内栖鳳、狩野芳崖、前田青邨、下村観山、中村彝、東山魁夷など挙げたらキリがありません。
今回は企画展を見ましたので無料でしたがこの常設展だけなら420円で楽しめます。個人的には東京国立博物館の本館の常設展(600円)と此処の常設展が値段も作品も素晴らしいと思います。両館とも特別作品は別ですが写真も撮れます。
前が皇居でゆったりしたガラス張りの休憩室からお堀、皇居の緑を見るのも好きです。
今回の展示
http://www.momat.go.jp/Honkan/permanent20130810.html#advice
皇居のほとりにあります近代美術館では14日まで竹内栖鳳展が開催中です。京都生まれで四条派、円山派、西洋美術などを取り入れた日本を代表する画家。
今回は1957年の回顧展以来の大規模な展覧会だそうで100点近くの作品、スケッチ帳などが展示されています。
今回はとても解りやすい展示で若い時の順番に展示されています。個人的には若い時期の絵の方が私は好きです。猫や象、狐、ライオンなどの描写は繊細で素晴らしい。
生意気な言い方をすれば風景画は個人的には?、この人の屏風はどこで使うんだろうと感じてしまう。最も我が家では使う場所もないか。円熟期になるほど絵がつまらなくなる。
スケッチ帳は沢山出展していますがこの方のスケッチは大まかな描き方であとで思い出す材料的なものだったんだろうか、そして写真も沢山フアイルしているようで動きは無理でしょうが外観は写真だったんでしょうか。
沢山の出典ですので良いもの、有名なもの、個人的な好きなものがある反面、個人的に好きになれない、飛ばすものも多い。
いろいろ触り過ぎ、設定を外してしまったのか、写真は今のところ載せられません。
11月4日まで松山のセキ美術館名品展を開催しています。加山又造の作品を中心に日本画は横山大観、上村松園、川端龍子、前田青邨、伊東深水、東山魁夷、平山郁夫、今野忠一などそうそうたるビックネームが。
洋画では黒田清輝、藤島武二、梅原龍三郎、小磯良平、岡鹿之助、荻須高徳などです。荻須高徳は私は初めて聞く名前ですが佐伯祐三のような絵が出展。
点数が40点位でこじんまりした美術館ですが私的にはちょうど見やすい大きさです。今回はビックネームが多く平日ですと他の美術館に比べゆっくりできますが今回は多くのお客様が来場していました。
加山又造の絵ではチラシになっている夜桜、支笏湖の沢山の鵜を描いた冬、中央公論の表紙原画の2月の雪をかぶった梅の枝にピンクの蕾、4月の桜、七月の柳の絵が良かった。
 9月15日から12月15日まで3期に渡り開館50周年記念の展覧会として開催されます。10月14日までが第一期になります。
9月15日から12月15日まで3期に渡り開館50周年記念の展覧会として開催されます。10月14日までが第一期になります。
川端龍子は明治18年和歌山で生まれ、10歳で母と共に上京。明治42年には大田区山王に住まいを移し、大正9年に今の地に転居してから80歳で亡くなるまで大半を大田区のこの地で制作に励んでいました。
昭和38年描いた時の光の状態でお客様に見ていただきたいという事で、自身が設計し建てた喜寿を記念して建てられたものです。没後青龍社が運営、平成2年青龍社解散に伴い記念館、所蔵作品を大田区に寄贈されました。
 今回第一期の目玉は「鳴門」「踏切」が展示されています。鳴門は昭和4年の制作の大屏風で鮮やかな青が全体を占めていますがその分波の白が激しく飛び回っているような躍動感のある図。
今回第一期の目玉は「鳴門」「踏切」が展示されています。鳴門は昭和4年の制作の大屏風で鮮やかな青が全体を占めていますがその分波の白が激しく飛び回っているような躍動感のある図。


 踏切は大正3年の29歳時の制作で大森駅の踏切を人力車、大八車、天秤棒の売り子、袴の学生などが線路を渡る龍子らしからぬ絵です。左下の建物の屋根、一際大きい紅葉している木。龍子の躍動感のある絵とはまるで違います。
踏切は大正3年の29歳時の制作で大森駅の踏切を人力車、大八車、天秤棒の売り子、袴の学生などが線路を渡る龍子らしからぬ絵です。左下の建物の屋根、一際大きい紅葉している木。龍子の躍動感のある絵とはまるで違います。
 龍子の絵といえば大作で何処からでも多くの人が見られる会場主義です。今回も広い会場には13点の展示です。入場料200円、月曜休館。此処は時間で無料の龍子アトリエ見学ツアーもあります。(10時、11時、14時)
龍子の絵といえば大作で何処からでも多くの人が見られる会場主義です。今回も広い会場には13点の展示です。入場料200円、月曜休館。此処は時間で無料の龍子アトリエ見学ツアーもあります。(10時、11時、14時)
東急の五島慶太氏が収集した作品の展示する美術館。この秋は禅宗の美と題して掛け軸を中心に展示しています。国宝3点、重文20数点の立派な展覧会です。
残念ながら私には白隠の達磨図位しか解らず、自分で良いなぁという作品も少ない。お経の巻物になればもっと解りません。
ただ、お坊さんの書が何点かありますがとても達筆です。偉いお坊さんは、写経も真面目にやっているからかと一人納得してしまいました。機会があれば菩提寺の坊主に書いてもらおうかと、けしからぬ事を考えました。きっと下手だろうなぁ。
まだ秋といっても美術館の庭園は色づいてはいませんが今日は久しぶりに庭園を散策しました。解らない絵などよりこの庭の風にあたっているのが気持ちが良かった。
今回は東急大井町線散策で上野毛駅の周辺散歩で招待券もありお邪魔しました。次回は「光悦―桃山の古典」が10月26日から12月1日まで開催予定。これも難しそうだなぁ。
五島美術館http://www.gotoh-museum.or.jp/exhibition/open.html
8月は夏休みで休館だった川崎砂子の里資料館では9日から28日まで富士山の描かれた絵画、浮世絵を展示しています。
富士山の絵画と言うと横山大観を思い出しますが入ってすぐドーンと飾っているのは片岡球子おばちゃまの富士山3点。その他に 奥村土牛の絵も。斉藤さんは浮世絵だけでなくいろいろな絵画をコレクションしているんだと驚き。
広重の不二三十六景(12点)、六十余州名所図会(3点)五十三次名所図会(12点)富士三十六景(9点)他展示は63点。
浮世絵の富士山といえば葛飾北斎の富嶽三十六景ですが今回は4点のみ、意識的に北斎を外し、広重を今回はメインに持ってきたようです。北斎というより宗理時代の茶屋の富士は初めて見ました。
開催中にもう一回位はゆっくり見たいと思いました。また10月1日にはすぐ近くに東海道かわさき宿交流館がオープンします。共に入場無料。砂子の里資料館は日曜休み、交流館は月曜休み。
渋谷のBunkamuraザ・ミュージアムではポーラ美術館コレクションを中心にしたレオナール・フジタ展(藤田嗣治)を10月14日まで開催中です。この展覧会は一度見に行こうと思いましたが招待券を忘れてしまいました。
東急渋谷駅から109方面に歩いていたら偶然小さな変わった自転車のまた派手な洋服の作詞家東海林良さんに遭遇。お互い元気で良かったと久しぶりの再会。大森の正助市場で会うことを約束して別れる。多くの人が歩く雑踏の中での偶然でした。(写真は右から東海林さん、正助社長、菅官房長官、左がパパリン)
今回の展覧会は想定通りフジタと言えば乳白色の裸婦、猫です。期待を裏切らない展示です。またパリでの友人で互いに影響し合ったアンリ・ルソー、モディアーニ、パスキン、キスリング、スーティンなどの絵も展示、スーティンは知りませんでした。一番影響を受けたのはピカソだったような気がしますが。
最後には15cm角のフをァイバーボードにパリの様々な仕事をする子供達の姿が丁寧に描かれています。全部で95枚。子供が仕事をする訳でもなく藤田の空想の世界のようです。此れをアトリエの壁一面に描いたようです。
藤田の子供たちの顔はとても印象の強い、インパクトのある顔です。フランス人はこんな顔をしているんでしょうか。
またスペインで買ったドアにも同じような横長の絵を貼って楽しんでいたようです。
Bunkamura1階ギャラリーでも藤田嗣治の版画の販売がありました。ちょっと覗きましたが色付きは2百万円台、白黒でも数十万と目玉が飛び出す値段がついています。日本でも海外でも人気の作家の値段は凄い。それが売約済みの印が結構あるのには驚きます。
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |

