美術館・鉄道・お城・お相撲・お友達の話など趣味のブログです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
奇想の絵師歌川国芳の門下展―礫川浮世絵美術館
 都営大江戸線春日駅近くの礫川(こいしかわ)浮世絵美術館では奇想の絵師歌川国芳の門下の展覧会です。25日までが1部で12月1日から25日までが2部になります。
都営大江戸線春日駅近くの礫川(こいしかわ)浮世絵美術館では奇想の絵師歌川国芳の門下の展覧会です。25日までが1部で12月1日から25日までが2部になります。
あまり門下の人の名は知りません。歌川芳虎、芳政、芳艶、芳員、芳秀、芳春、月岡芳年、河鍋暁斉、落合芳幾、などです。国芳は今年没後150年で色々な美術館で開催しました。来月から六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで最後の仕上げみたいに開催されます。
この礫川浮世絵美術館は小さい浮世絵専門美術館ですがそんなに混まなくゆっくり拝見できる好きな美術館です。場所柄中々行けないのがたまにきずですが今回は都営1日パスがあり大江戸線の新宿からすぐですからお邪魔出来ました。
http://homepage2.nifty.com/3bijin/
織田一磨展―平木浮世絵美術館
 豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。
豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。
私は織田一磨、石版画とも初めてです。石版画は明治後半までは最先端の印刷技術でしたが写真製版技術と共に衰退をしていったようです。今回の東京風景、大阪風景は日本の版画史にとっても記念碑的な作品のようです。
此処の美術館も小さい浮世絵美術館ですがとても質の高い作品を所蔵しています。私にはゆっくり見られますが場所が都内の中心部なら混雑をしてしまうだろうという企画展も良いものが多いです。
http://www.ukiyoe-tokyo.or.jp/
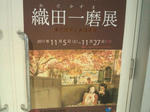

あまり門下の人の名は知りません。歌川芳虎、芳政、芳艶、芳員、芳秀、芳春、月岡芳年、河鍋暁斉、落合芳幾、などです。国芳は今年没後150年で色々な美術館で開催しました。来月から六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで最後の仕上げみたいに開催されます。
この礫川浮世絵美術館は小さい浮世絵専門美術館ですがそんなに混まなくゆっくり拝見できる好きな美術館です。場所柄中々行けないのがたまにきずですが今回は都営1日パスがあり大江戸線の新宿からすぐですからお邪魔出来ました。
http://homepage2.nifty.com/3bijin/
織田一磨展―平木浮世絵美術館
 豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。
豊洲にあります浮世絵専門の美術館ですが今回は大正時代の石版画のパイオニア織田一磨の版画展です。タイトルは「東京風景と大阪風景」です。浮世絵がその当時の生活を描いたと同じように石版画で東京、大阪の情景を描いています。私は織田一磨、石版画とも初めてです。石版画は明治後半までは最先端の印刷技術でしたが写真製版技術と共に衰退をしていったようです。今回の東京風景、大阪風景は日本の版画史にとっても記念碑的な作品のようです。
此処の美術館も小さい浮世絵美術館ですがとても質の高い作品を所蔵しています。私にはゆっくり見られますが場所が都内の中心部なら混雑をしてしまうだろうという企画展も良いものが多いです。
http://www.ukiyoe-tokyo.or.jp/
PR
今回はそのコレクションからの展示です。やはり多くの浮世絵が展示されています。初めてみるものや何度か見たものもありますが今回が浮世絵は一番多いようです。何度か見ていますが1冊全部浮世絵のこの冊子は毎回凄いと思っています。
お相撲さんは九州へ行っていますから閑散とした幟もなく寂しい両国ですが来月には東京へ帰ってきます。来月は年末恒例の激励会、部屋では餅つきがあったり新番付が発表されたりと賑やかになるでしょう。
12月から「絵で楽しむ忠臣蔵」「歴史の中の龍」1月からはNHK大河ドラマ50年「平清盛」展のようです。
目白駅前、丁度学習院のまん前の5階建てのビルです。今日は夜まで色々廻りますがまだ少し時間があるので入って見ました。このビルの入居はこのエスケースタンプと後数件だけで殆どが閉まっています。1階は入居ゼロでエスカレーターだけが寂しい音を出しています。
使用済み古切手、初日カバーなどはダンボールの中です。新しい切手、コインはショーケースの中です。最初は切符があるとは分からず古銭、紙幣を探していましたが、鉄道切符のダンボールもありました。
とりあえず、幾らするのか確認すると値段が付いていても大体100円だそうです。こりゃ安い、次へ行く時間もあり適当なところで精算、かなりありましたが二千円でお釣が来ました。
新宿歴史博物館では年に数回区内散策を実施しているようです。今回は「平塚運一と目白文化村」を中心に約3時間散策をしました。
今回の集合場所は都営大江戸線落合南長崎駅A2出口でした。この所aibikiさんの故郷、区民フェスタでの長崎のお土産と何となく長崎が絡みます。近くには西武池袋線の東長崎駅もあります。沿革は分かりませんが長崎と区別する為東長崎、南長崎があるようで北、西はないようです。
20名位の参加で2つの班に別れ案内をして頂きました。棟方志功が先生と呼んだ版画家平塚運一が今回のメインです。私は平塚運一の名前は知りませんでした。落合は江戸時代より散策の地で浮世絵「落合の蛍」や江戸名所絵図などにも描かれているようです。
平塚運一は日本創作版画の生みの親と言われ明治38年島根県松江市生まれ102歳の生涯を版画にささげた木版画画家だそうです。昭和3年~昭和15年まで日本各地で版画講習会を開き多くの版画家を育成し棟方志功もその一人だそうです。
昭和37年から30年間アメリカ、ワシントンDCで生活し「裸婦百態」「裸婦鏡」などで有名になったようです。平成7年に帰国し百歳展を開催、この落合のアトリエで102歳の翌日に亡くなり、今回参加の方に親戚の方がいて丁度今日、11月18日が命日だそうです。
アトリエの中は誰も住んでいなく見学もできず高い塀の中の木々に埋もれている感じです。中には収集した古代瓦が沢山ありこのアトリエも瓦乱洞(がらんどう)と呼び門には薄くなっていますが仏教版画の仲間の会津八一が書いたそうです。
岩崎版画のすぐ先が自性院です。此処は平塚運一のお墓があります。また猫地蔵で有名なお寺さんです。真言宗 西光山 無量寺自性院です。太田道灌が江古田ヶ原の戦いの時日が暮れて道に迷った時一匹の黒猫が道案内をして草庵に1夜を過ごし江戸城に帰城出来ためその後も黒猫を大切に飼い、死後も供養の為その草庵(自性院)に地蔵尊を奉納したと伝えられています。毎年2月3日節分の日に開帳されます。今回は特別のようです。
此処では佐伯祐三のアトリエは新宿区立として保存展示されています。また外観だけでは渡辺玉花邸などがあります。残念ながらこのお二人の名前も初めて聞きました。
地下の説明を受けた場所はギャラリーになっていて「歌川国芳」展を開催しています。入場無料、版画の販売もしています。
約三時間、私より年上の方々で新宿にお住まいの方が多かったですがのんびり初めての落合を散策が出来ました。また新宿歴史館では所蔵している平塚運一と落合の版画家展を来月12月10日~24年2月5日まで開催される予定です。
入場料無料、詳細はhttp://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=372
早朝より大門から都営大江戸線に乗り落合南長崎駅から新宿歴史博物館の「第3回落合の追憶 棟方志功が先生と呼んだ版画家・平塚運一と目白文化村を訪ねて」に参加しました。
9時から12時頃までの散策でした。平塚運一アトリエ~自性院~目白文化村渡辺玉花・佐伯祐三アトリエ記念館~アダチ版画研究所と言うコースです。
終了後はJR目白まで歩き駅前の丁度学習院の前のビルの5階のエスケースタンプで鉄道切符を購入、Jr目白から新宿へ出てまた都営大江戸線で春日駅で礫川浮世絵美術館(奇想の絵師歌川国芳の門下展)~両国駅下車(国技館相撲博物館で酒井忠正コレクション)~月島下車して有楽町線で豊洲(平木浮世絵美術館)~月島~JR代々木~JR渋谷~三軒茶屋(友人と一杯)と版画とJR/地下鉄の一日でした。
早朝から家を出て9時半帰宅、地下鉄も乗りましたが良く歩いた一日でした。多分此れだけ色々な現代版画、浮世絵を1日で見たのは初めてです。此れに原宿の太田記念美術館でも行けば都内の常設浮世絵美術館を制覇でした。
明日は天気が雨だそうですから1日、切符の整理と猫の棚作りでもと思っています。今日は歩きすぎました。
9時から12時頃までの散策でした。平塚運一アトリエ~自性院~目白文化村渡辺玉花・佐伯祐三アトリエ記念館~アダチ版画研究所と言うコースです。
終了後はJR目白まで歩き駅前の丁度学習院の前のビルの5階のエスケースタンプで鉄道切符を購入、Jr目白から新宿へ出てまた都営大江戸線で春日駅で礫川浮世絵美術館(奇想の絵師歌川国芳の門下展)~両国駅下車(国技館相撲博物館で酒井忠正コレクション)~月島下車して有楽町線で豊洲(平木浮世絵美術館)~月島~JR代々木~JR渋谷~三軒茶屋(友人と一杯)と版画とJR/地下鉄の一日でした。
早朝から家を出て9時半帰宅、地下鉄も乗りましたが良く歩いた一日でした。多分此れだけ色々な現代版画、浮世絵を1日で見たのは初めてです。此れに原宿の太田記念美術館でも行けば都内の常設浮世絵美術館を制覇でした。
明日は天気が雨だそうですから1日、切符の整理と猫の棚作りでもと思っています。今日は歩きすぎました。
左上の写真はドンキのビルです。隣は浅草ですがねずみ小僧でしょうか、どちらも泥棒のようです。ドン・キも元々は「泥棒市場」と言うお店から大きくなったんだと納得しました。
二段目左はお弁当屋さんですが法事の食事もやっているようですが「さよならは、もう高くない」というフレーズに驚きました。値段が安い事を言いたいのでしょうが余りにも乱暴な言葉です。
真ん中のサンタさんは何故か痩せています。案山子かと思ってしまいました。でも此れは大森の公園の前のクリスマスデコレーションです。
左は工事中の建物です。今は建設面積によって緑地を設けないといけないようで壁に緑地を設けた変わった建物です。後から蔦などを絡ませるのはありますが建設中から絡ませています。
右の写真は「おでき薬局」という大森入三銀座商店街に有ります薬局です。この名前はテツの間では有名なお店です。国鉄の時代に京浜東北線、山手線の殆どの駅の線路の柱に「おでき薬局」と看板を出していました。あとは「ノザキのコンビーフ」です。
ノザキは有名ですがおでき?と皆さんが思っていたようです。お相撲の関係で此処の番頭さんのT氏とたまたまご一緒していました。昔は安かったので看板を出していたとか言う程度だったようです。でもお店のなまえに「おでき」はインパクトがあります。
私も昔彼から調合してもらった水虫の薬で治りました。今ではおできとは言わないで吹き出物とかアレルギーとか言うようですがこのお店は今でもわざわざ訪ねてお客さんが大勢来るようです。
町田駅からバスに乗り町田自体が郊外ですがもっと郊外の里山風の中にあります。初めてでしたからバス停から400M坂道を歩きます。まだ紅葉には早く、一部色付いている程度でススキがまだプラチナ色になっていません。
明治からのカットグラスの歴史、ヨーロッパからの回転工具の導入、技術により江戸切子へと変遷していく過程を作品を見ながら学べるようになっています。昭和前半からの商品などは自分の家にあったような気がする物ばかり、色がくすんでいます。
かみさんは作る行程に興味を示していましたが私はあの美しい切子を楽しみに見るつもりでした。最後に二ヶ月に一度いく教室の鍋谷聡氏の作品が展示されていました。ちょっとこれを見てほっとしました。
博物館は雑木林の麓?にあるんでしょうか、一寸した里山を感じました。1時間以上掛けて3,40分で退出しかみさんは横浜へ、私は猫の待つ我が家へ帰宅。
大田区内の散歩コースも約三分の一は終わりました。此れからは馬込ウォーキングコースとしてコース選定をしていきます。
①大田文化の森ー②大田区立川端龍子記念館ー③大田区立熊谷恒子記念館ー④大田区立郷土博物館ー⑤長温寺ー⑥旧馬込小学校時計台ー⑦庚申燈篭(神明社)-⑧万福寺ー⑨富士講燈篭ー⑩名馬磨墨塚ー大田文化の森
このコースは馬込九十九谷と言われる谷の多い場所で上り下りがかなりきつくなります。間違えるとまた坂を登らなくてはならなくこの時期には、体力づくりにお勧めです。
昔、太田道灌が江戸に城を築城する時の候補地でもあり案内で九十九谷と言われ縁起が悪いとされたとかの話もある場所でお城の防御としては最適な場所でもありました。残念ながら江戸氏の館跡があった現皇居周辺が造営され江戸城になったと言われています。
JR大森駅から歩くかバスで大田文化の森で下車し前の臼田坂から始まります。大田文化の森は以前は此処に大田区役所がありましたが手狭な為現在はJR蒲田駅前の立派なビルに移転しています。
新しく建物を建て区民が自主運営する催しなどを行なっています。毎月第一金曜日に私は此処で行なわれる朗読の会を楽しみにしています。その他にスカッシュなどの運動やホールでは合唱、演劇などの発表会、本館では陶芸教室、図書館などもあるようです。
今回のコースは日本画家の川端龍子記念館、此処では企画展を見た後、時間により前の龍子のアトリエを学芸員が案内をしていただけます。中々画家のアトリエを見る機会は少ないと思います。現在は耐震工事中で12月21日まで閉館です。
また美智子皇后陛下のかな書の先生で現代女流かな書の第一人者熊谷恒子記念館もあり此処は自宅書斎がそのまま見る事も出来、交流の広さから多くの方の書も展示されています。昨年の企画展では皇后陛下もお忍びでお見えになったそうです。但し庭には降りられません。
郷土博物館では六郷用水、馬込文士村、大田区のモノづくり、海苔養殖、昔の生活、戦争時代の暮らしなどが展示されています。
歴史のあるお寺も幾つか廻りますが庚申塔が意外に多くある地域でも有ります。
以上のような特徴を持ったコースですがやはり道が狭く車が多く気をつけて歩かないと危ないところもあります。この周辺は文士村の住人の碑も多く見られます。
時間としては3時間半を基本としますが記念館などで時間を取るとやはり半日コースになります。近隣には小さい公園、コンビニもありますのでトイレはそんなに心配は無いと思います。
食事はコンビニや美味しい自家製のパン屋さんや蕎麦屋などがあります。ただ長温寺、万福寺周辺では食べ物は少なくなります。入場料も区立ですから無料から200円です。
次回は各施設の住所、特徴、見所を書きます。
①大田文化の森ー②大田区立川端龍子記念館ー③大田区立熊谷恒子記念館ー④大田区立郷土博物館ー⑤長温寺ー⑥旧馬込小学校時計台ー⑦庚申燈篭(神明社)-⑧万福寺ー⑨富士講燈篭ー⑩名馬磨墨塚ー大田文化の森
このコースは馬込九十九谷と言われる谷の多い場所で上り下りがかなりきつくなります。間違えるとまた坂を登らなくてはならなくこの時期には、体力づくりにお勧めです。
昔、太田道灌が江戸に城を築城する時の候補地でもあり案内で九十九谷と言われ縁起が悪いとされたとかの話もある場所でお城の防御としては最適な場所でもありました。残念ながら江戸氏の館跡があった現皇居周辺が造営され江戸城になったと言われています。
JR大森駅から歩くかバスで大田文化の森で下車し前の臼田坂から始まります。大田文化の森は以前は此処に大田区役所がありましたが手狭な為現在はJR蒲田駅前の立派なビルに移転しています。
新しく建物を建て区民が自主運営する催しなどを行なっています。毎月第一金曜日に私は此処で行なわれる朗読の会を楽しみにしています。その他にスカッシュなどの運動やホールでは合唱、演劇などの発表会、本館では陶芸教室、図書館などもあるようです。
今回のコースは日本画家の川端龍子記念館、此処では企画展を見た後、時間により前の龍子のアトリエを学芸員が案内をしていただけます。中々画家のアトリエを見る機会は少ないと思います。現在は耐震工事中で12月21日まで閉館です。
また美智子皇后陛下のかな書の先生で現代女流かな書の第一人者熊谷恒子記念館もあり此処は自宅書斎がそのまま見る事も出来、交流の広さから多くの方の書も展示されています。昨年の企画展では皇后陛下もお忍びでお見えになったそうです。但し庭には降りられません。
郷土博物館では六郷用水、馬込文士村、大田区のモノづくり、海苔養殖、昔の生活、戦争時代の暮らしなどが展示されています。
歴史のあるお寺も幾つか廻りますが庚申塔が意外に多くある地域でも有ります。
以上のような特徴を持ったコースですがやはり道が狭く車が多く気をつけて歩かないと危ないところもあります。この周辺は文士村の住人の碑も多く見られます。
時間としては3時間半を基本としますが記念館などで時間を取るとやはり半日コースになります。近隣には小さい公園、コンビニもありますのでトイレはそんなに心配は無いと思います。
食事はコンビニや美味しい自家製のパン屋さんや蕎麦屋などがあります。ただ長温寺、万福寺周辺では食べ物は少なくなります。入場料も区立ですから無料から200円です。
次回は各施設の住所、特徴、見所を書きます。
シネマの名匠の方は外国映画と日本の映画の駅を取り上げています。外国映画はそんなに見ていませんし駅を気にしてみてはいませんでした。
小説を映画を鉄道が走るは大分前の小説が多く読んでいないものも多くあります。また、乗ったことのない列車、路線も廃線になっているものも当然多く乗っていないところも多く有ります。
でもこう言う本を読むとまた旅に出て行きたい衝動に駆られます。読みながら此処へ行った時は映画でこんなドラマが展開していたんだ。またロケは大変だっただろうしそこを巡れば良かったなど思い残したりします。
仕事で行く人は年がら年中乗れるでしょうが私の仕事ではそう言う事も少なく殆どが観光で歩いていましたからどうしても特殊なところ、時間的制約や離れているところはやはり行けませんでした。
駅舎も殆どゆっくり見ることも無く観光地へ向かってしまいます。今も城の旅なら降りて直ぐ城に向かって歩くかバスに乗ってしまいます。もう少し余裕を見た旅をしていればと今更ながら悔やんでも。
知らない事が多かった2冊ですが何となく自分が主人公で廻っているような楽しい時間でした。
JR大森駅山王口―①品川歴史館―②大森貝塚(品川、大田)―③尾崎士郎記念館―④徳富蘇峰旧邸(山王草堂記念館、公園)―⑤天祖神社(馬込文士村レリーフ)―⑥薬師堂―⑦大田区立山王会館(馬込文士村資料、大田百景)―⑧熊野神社―⑨善慶寺―JR大森駅
⑦大田区立山王会館 山王3-37-11
立派なマンションで売れそこなったマンションをなぜか大田区が買って会議室や展示場として使用しているようです。此処には馬込文士村の資料が展示されています。また隣の部屋では大田区百景として大田区の画家、学校の先生などが描かれた絵が飾っています。
殆ど此処へ見に来る人はいないようです。文士村へは名前住所を書かされますが大田百景には書かされません。管轄が区の中で違うようです。お役所仕事の典型とバブル時の遺産の様な箱物を何で買ったんだと思うもので管理人が2人もいます。
文士村の資料は大田区立郷土博物館へ大田百景も郷土博物館か区民ホールアプリコで充分展示保管が出来そうです。無駄な箱物のようで余計な経費をかけています。
この地域の旗本木原氏が幕府の棟梁として日光東照宮造営の余材で社殿を建立したと伝えられています。元和期の建立とされていますが大田史話2によると元和二年之東照宮造営には関わっていないようです。
木原氏は現在の静岡袋井市の出で幕府の大工頭を務め紀伊の熊野社に仕える鈴木氏の一族で先祖ゆかりの深い熊野信仰から江戸に知行地が変わってそれをこの地へ持ってきたのでは考えられています。
境内には能舞台、力石、庚申塔などがあります。山王会館から山の頂上を歩きちょうど神社の裏手からになります。この方が下りたり登ったりがしないで済みます。
正面の鳥居から逆に急な石段を降りますと善慶寺の境内にでます。
日蓮宗 法光山 日法上人を開基として1292年建立。
この寺は新井宿義民6人衆で有名です。また初夏にはここでホタルも見られます。
延宝義民6人衆事件は永宝5年(1677)1月2日この地を治めていた直参旗本木原氏の年貢の厳しい徴収と大飢饉により直接将軍家綱に直訴をしようとした新井宿代表の6人衆は密告により捕まり打ち首となりました。直訴は大罪でひそかに20世日応上人が善慶寺で供養されました。毎年4月にお祭りが行われています。今年は4月10日供養のみでパレードは中止になりました。
間宮家の両親の墓を建立するということにして裏に6人の戒名が刻まれ墓の四隅に水が回るようにしてお参りが出来るようにした珍しいお墓があります。
墓石の四隅に水入れがあり前に水を入れると後ろにも流れるようにくり貫かれています。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カウンター
カテゴリー
最新コメント
最新記事
(04/17)
(04/17)
(04/16)
(04/15)
(04/14)
(04/13)
(04/12)
(04/11)
(04/10)
(04/09)
(04/09)
(04/08)
(04/07)
(04/06)
(04/05)
(04/05)
(04/04)
(04/04)
(04/03)
(04/03)
(04/02)
(04/01)
(03/31)
(03/30)
(03/30)
プロフィール
HN:
パパリン
性別:
男性
趣味:
なんでも収集
ブログ内検索
アーカイブ
アクセス解析


